mum&gypsy
穂村弘×マームとジプシー×名久井直子
ぬいぐるみたちがなんだか変だよと囁いている引っ越しの夜 東京公演 終演後トークイベント(1回目)
2020/12/12
穂村弘(歌人)×名久井直子(ブックデザイナー)×藤田貴大(マームとジプシー)
東京公演 アフタートーク
2019年 12月28日/キチム

藤田 こんにちは。今日は、クマに囲まれてしまって。
名久井 ぬいぐるみたちっていう感じで、着てみました。
(穂村さん・名久井さんがお揃いのクマのイラストが書かれたニットを着用)
穂村 お揃いを着てみました。
藤田 そういうこと、先に言っておいてくださいよ。
穂村 お客さんにこれが二人のナチュラルな状態だとおもわれちゃうよね。
名久井 確かに(笑)。今日はアフタートークのために二人で揃えてきました。
藤田 わざわざありがとうございます。
穂村 今日も感動しました!
名久井 今年に入って何回目の公演なんだろう?
藤田 今年に入ってからだと、京都2か所、三重、長崎、岩手と巡ってきてからの東京なので、ツアーとしては5か所目です。
名久井 回を重ねるたびに作品のチューニングが変わっていくというか、何度も見てるのに毎回新鮮な感じがしますね。
穂村 微調整、微調整を重ねて。
名久井 私が最後に見たのは長崎公演ですが、そこからもだいぶ変わってきていますね。
藤田 そうですね。
穂村 作中の映像で出てくるおじいさんは、僕の父なんです。
藤田 それ、穂村さんアフタートークで毎回言いますが、あれが穂村さんのお父さんじゃなかったら誰なんでしょう(笑)。
穂村 もしかしたら俳優さんかなって思うひともいるかなと。あのおじいさんは父で、撮影場所はリアル実家なんです。取材にみんなが来たんだけど、マームと言えばおしゃれなイメージがあったから、撮影場所が実家で大丈夫なのかなって。ウーロン茶がね、箪笥の上に見えましたね。
藤田 お父さんが、僕らが行くからって用意してくださっていたものです。
穂村 あのウーロン茶は小道具じゃないんですよ。父の話もだし、映像に出てくる母の育児日記だったり、僕の小学校の作文だったり、子供の頃のアルバムとか、そういうリアルな僕の素材をひっくり返してこれだけの作品を作り上げる手腕というのか。
名久井 そうですよね。このマームの取材がなかったらブリギッテのことも分からなかった。
藤田 そうですよね。
穂村 あれはショックでしたね。父がドイツで働いていた独身時代に、ものすごい美少女のドイツ人の彼女がいたなんて。なんでこっちにしなかったの!? っていう。映像の中で父は、日本のボットン(トイレ)のことをすごい気にしていたけど、そんなの気にしないで連れてきちゃえばどうにかなったと思うし。ただ……そうなってたら僕はいない。
名久井 そうですね。
穂村 結果的に、よかった。
藤田 そうなんですよねー。
穂村 不安にならないんですか? ああいうおじいさんの取材。
藤田 いや、すごく楽しかったです。
穂村 どんな話が出てきたとしても、大丈夫な自信があるんですか? 80代後半のおじいさんの話を聞くってなかなか勇気がいることですよね。
名久井 勇気と根気がいりますよね、多分。
藤田 ちなみに、お父さんの取材は穂村さんに聞き手をお願いしたのですが、その時の穂村さんを青柳がコピーして演じています。
穂村 そうそう。父の映像と青柳さんが話すシーンの青柳さんは、取材の時の僕なんです。
藤田 お父さんには穂村さんと話して欲しいと最初にお伝えしたのですが、取材中に僕らもその場にいたので、僕らにも話しかけてくれていましたね。映像の中で、お父さんが途中少し目線を逸らすのは僕らに話してくれているからです(笑)。
穂村 父は多分あまり状況が分かってなくて、藤田さんは見た目も若いせいもあって、少年のように思っている節があり、藤田さん以外のマームたちも年齢不詳だから、少年少女が家に来たみたいな感じだったんじゃないかな。

(ティモシーの着ぐるみが水を持って登場)
名久井 ティモシーありがとう。
藤田 「ティモシー」っていうのは映画版『ダンボ』に出てくるダンボの友だちのネズミです。この着ぐるみは中国から届いたんですけど、これがあのティモシーだってお客さんはあんまり分かってくれない。
(ティモシー手を振って退場。)
名久井 ティモシー。ありがと。
穂村 藤田さんって、どんなものでも絶対演劇にしてしまうよね。それってなんなんだろうね?
名久井 なんでも拾うよね。そうそう。
穂村 だからどうやってやってるのかなって。
藤田 どうやってやってるんだろうな。
名久井 私のシーンであるChapter 3.5のところで、パントーンの色見本が出たり消えたりしていく映像が流れてたと思うのですが。あれも私が捨てようと思っていたものが拾われていて、それを使ってる。本当に無駄にしないなって。
藤田 僕ら、名久井さんと穂村さんの資料はめちゃくちゃ持ってますよ。
名久井 本当にすごいと思う。
穂村 名久井さんのシーンの話をすると、あのシーンは青柳さんが名久井さんを演じているんだけれど、最初の一声で今までとは違うひとになったっていうのが分かる。
藤田 青柳には穂村さんや名久井さんの取材に基本全部立ち会ってもらっています。だからなのかな、その場のその感じをそのままトレースしていけるんですよね。
穂村 青柳さんが「私が作品の最終的な出口だ」という、感動的なシーンがあったけど、始まったらもう我々は指一本作品に触れることはできないから、最後はもう青柳さんに託すしかないっていう。
名久井 うん、もう私達は原材料くらい。
穂村 もう、青柳さんは特異能力者だよね。
名久井 本当にね。
藤田 そうですね。青柳がいるからこそできることがあるじゃないですか。それは青柳だけの話ではなくて、この俳優さんとだったらとか、このチームだったらとか、それぞれできることやキャパシティがあるんだと思います。ただ青柳がいると、やれることが増えます。テキストを一言口にすれば覚えるので、僕としても足し算引き算がしやすいんですよ。
穂村 僕が書いているものって、韻文なんだよね、詩とか短歌とか。通常の散文に比べて非常に扱いにくくて、普通に説明しようと思ったら説明しにくいものだと思います。それを藤田さんの演出では、普通ではない、タイミングとかテンポとかを同時に発生させて、まずは通常の「理解」を観る者に断念させていますよね。だからこそ、お客さんは普通の文章を読むのとは違うカタチで作品をキャッチしていくしかないのです。この作品は、いつもの脳の回路で理解しようとしたらオーバーするだろうし、全く理解できないだろうから、自然とお客さんもそういう観方に順応していくんだよね。それで最終的には必ず儚く消えるけど、永久欠番みたいな感動ポイントに強制的に持って行かれる。
藤田 穂村さんはこのことについていろんな言葉で話してくれるんですけど、とても納得できることが多くて。穂村さんの歌集やエッセイを読んでいると、書かれてあるモチーフに日々の移ろいを感じます。一冊を通して大きなストーリーを扱っているわけではないのだけど、穂村さんは日々、どういうことを感じて、どういう出来事があって、ということを断片的に想像しながら読むわけですよね。短歌という表現における時間の扱われ方はもっと独特で、縮こまったり飛躍したりが楽しいですよね。そうやって受け取ったニュアンスを、演劇でもできないのかなって思っていました。そもそも穂村さんや名久井さんを演劇にするといっても、ストーリーなんてあるのか分からないですよね。
名久井 そうですね。
藤田 だけど、ふたりと話す時間は僕にとって貴重で。穂村さんがこういうことを言ってたよ、名久井さんがこういうことを言ってたよって、マームとジプシーに持ち帰ってみんなに話すんですよ。僕は演劇を通してじゃないとそのひとを捉えることができないので、演劇という道具をつかって、さらにふたりを知っていきたいと思っているんですよ。つくっていくなかで、どんどんふたりから影響を受けていくわけなのですが、そうすると演劇における"当たり前"というのは当たり前ではないなと気づいていくんですよ。それは言葉についても、もっと細かく言うと名久井さんを通して知る紙へのこだわりとか。だからこの作品は「ストーリー」をどうしていくかと頭でかんがえていくより、もっと身体的な感覚で捉えていったことをそのまま表現したいな、と。時系列としては真夜中から始まって翌朝になるという流れは作りました。でも青柳が演じているのは「青柳いづみ」なのか「ある女性」なのか、その女性はもしかしたら穂村さんと付き合っていたのかどうかとか、いわゆる分かりやすいキャラクター設定のようなものは曖昧にして、だれにでも見えてもいい状態をつくりたかった。
穂村 いつも、これ気になってしまうから、話してしまうことなんだけど、青柳さんが名久井さんのコピーをする時もね、名久井さんが言い間違えたりためらったりするところも全部コピーしてるんですよ。お客さんから見ると、「あ、噛んだ」って思いそうなんだけど、あれ、噛んだのはリアルな名久井さんであって、それを青柳さんの演技の中で正確に噛まずに噛んでるわけなんですよ。父が映像の中で胸を叩いて、叩いた場所にちょうどマイクがあったのでバンバンって変な音がするんですが、ここで青柳さんも同じタイミングで胸をバンバンって叩くのも、叩かないといけないのかなって。あれはなんなの? 間違いとかそういうものも、正確に保存しなくちゃいけないの?
藤田 それは僕のくせみたいなものだと思いますね。そのままのほうがいい、あまりノイズは消さないほうがいい、みたいな。それは、なんだろうね? 整えていけば整えていくほど、どんどん隙が無くなっていっちゃうから嫌なんですよね。
名久井 それは分かるかも。デザインとかでもあるよ。
穂村 12mmでね。トリミングしないとかね。
名久井 大竹さんの話はずっとここで繰り返されてるから、わたしの中ではだいぶ昔の話になってるんで、すごく胸がギューってなる感じです。
穂村 青柳さんは大竹伸朗のマネをする名久井直子のマネをしてるわけだからね。
藤田 青柳は大竹さんに会ったこともないしね。
名久井 『ラインマーカーズ』はとても印象深いお仕事でした。大竹さんからお花の絵が届いた時に電話もかかってきたんだけど、「あいつの詩には花が無いからよ、花を描いてやった」って言ってた。
藤田 そんな感じなんだ(笑)。
名久井 いやいや、大竹さんはすごく優しい方ですよ。

穂村 僕はいつも名久井さんのシーンで感動してしまいます。名久井さんはいつも、自分は作家ではないから自分は言葉持たない、と話しているんだけれど、そのことを舞台上で青柳さんが名久井さんとして言ったあと、今度は青柳さんが青柳さんとして「わたしも、、、言葉を持っていません、、、、、、」と言っていて、そのあと「言葉を持たないわたしたちは、、、、、、でも、、、書かれた言葉たちの、、、描かれた言葉たちの、、、、、、出口でもある、、、、、、」ってすごい絶妙な間で言うんだよね。
名久井 そうそう。疑問形で言うのもすごくいいよね。
藤田 ああ、あれなんなんだろう。
穂村 あれは演出じゃないの?
藤田 してないです。青柳は僕が意図しないところで、疑問系というか、疑問系とも言い切れない言い方で発語しだすんですよね。
穂村 そうなんだ。ちょと間をとって疑問にしてみたい、とか言ってないの?
藤田 言っていないです。
穂村 じゃあ、あれは青柳さんが言い始めたの?
藤田 そうですね。青柳に関しては、あまり喋り方とかは演出つけないですね。
穂村 じゃあ、舞台上で、本を開いてエイみたいにパタパタさせるのは?あれは藤田さんの担当なんだよね?
藤田 そうですね。あれは、藤田担当ですね。
穂村 そういうことが、観てる方は全然分からないわけ。
名久井 振り付けは藤田担当なんじゃない。
穂村 ああいう振り付けはやって見せるの? エイが泳いでるように本をパタパタするみたいな。
藤田 やってみせてはいないですね。
穂村 口で言うの?
藤田 口で言いますね。
名久井 エイみたいにパタパタとって?
藤田 エイみたいにって言ったかな? それはもう忘れちゃったけど、それ今答えるの、恥ずかしいじゃないですか(笑)
穂村 僕は、そういうところが知りたいんだよ!現実とそのパフォーマンスのギリのラインが分からない!
藤田 エイ、やって見せたかなあ? 忘れちゃいましたね。
穂村 アドリブは禁止なんだよね?
藤田 アドリブはもちろん禁止ですね。
名久井 青柳さんのアドリブは無いし、この作品に関してはほぼ私と穂村さんの言葉で構成されてて、藤田さんが書いた言葉ってすごく少ないですよね。
藤田 そうですね「いつだったか」くらいですね。あとは語尾だけとか。それぐらいの微調整ですね。
穂村 本当に、それすごいよね。
名久井 すごい。
藤田 そういう微調整が好きなんですよね。
名久井 本のことを少し言ってもいい? 演劇の中ではわたしのパートは少ないんですけど、このお芝居の副読本のような本を作っていて、物販でも販売しているんですけど、ぜひお手にとってご覧ください。
穂村 名久井さん渾身のデザインで。クロス装で箔押しで。
名久井 穂村さんの昔の写真をたくさん使わせてもらっています。ところどころかわいいハワイアンみたいな柄が入ってるんですけど、それは穂村さんのお父さんの当時のアルバムをスキャンしたものです。私も藤田さんの精神を見習って、どれも捨てない! あと、『ラインマーカーズ』のタイトルを決めた時の会議のメモも入ってます。
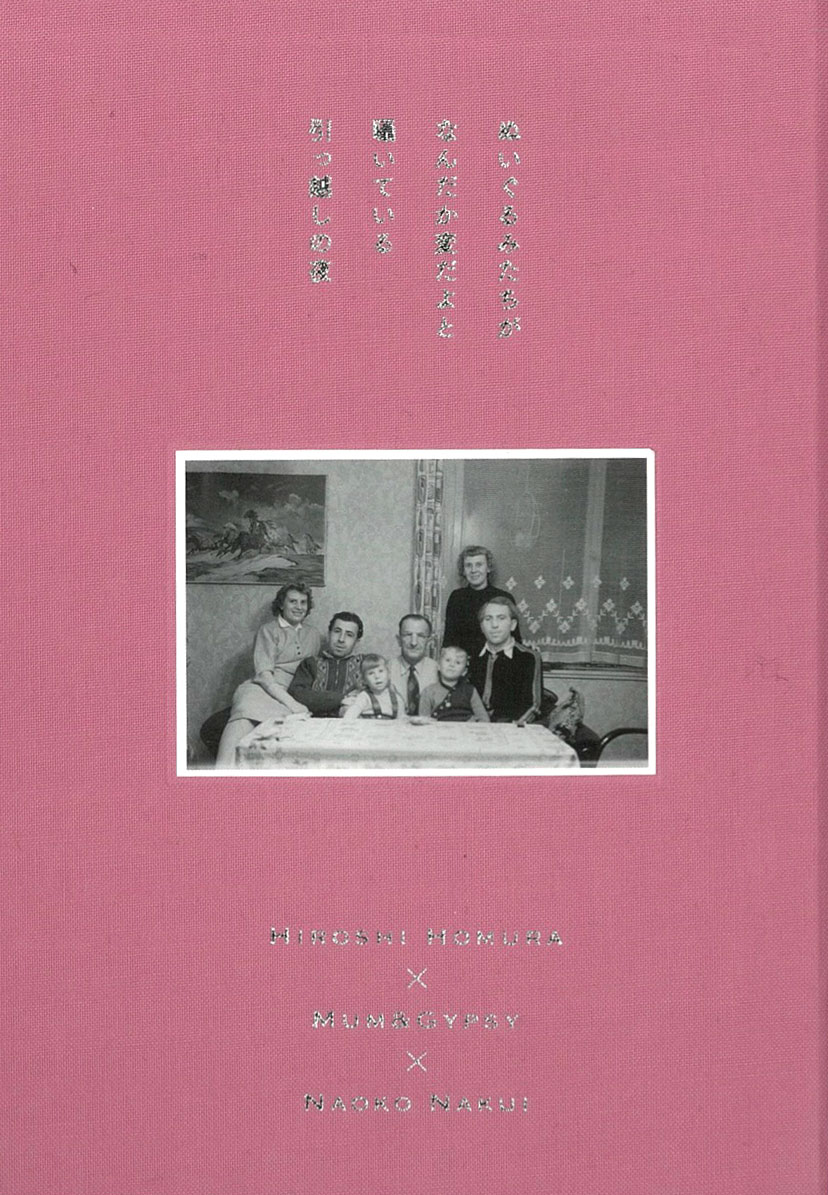
穂村 あのメモ、持っててくれたんだね。
名久井 あれね、なんとなく捨てちゃいけないと思って。色校とかは容赦なく捨ててるんですけどね。
藤田 確かあのメモ、名久井さんがかなり探してくれてやっと出てきましたよね。
穂村 さっきの話の続きはみんなもういいの? 青柳さんと藤田さんの作業のラインについての話。みんな気になってるよね。
名久井 気になるけどね、私はいちいち線は引きたくないかな(笑)
藤田 キチムでの公演の前は、岩手公演だったんですけど、みんなで公演が終わったあと、わんこそばを食べに行ったんです。それで、やっぱりわんこそばのシーンをどこかに加えなくちゃと、青柳と話してて。
穂村 それは加えなきゃいけないの?
名久井 もう意味が分からないよね。東京公演で「東家(わんこそばのお店の名前)」のエプロンしてて。
藤田 だって、穂村さんがエプロン買ってくれたんだもん。それはもうそういうフリだと思うじゃん。それで、入れるとしたらこのシーンのあそこかなっていう話をしてて、あそこじゃないかな? って僕は言っただけです。エプロンつけるとか、そういうところは全部青柳がやってました。引越しの時って旅行の時のテンションで買ったいらないものとかたくさん出てきて捨てるのに困るじゃん。
名久井 確かに。今回の作品にもキワキワのものたちが一気に出てきたね。
穂村 勝手に青柳さんがわんこそばのエプロンをつけてたみたいなことは絶対ありえない?
藤田 それはありえないですね。
名久井 それは怒るの? もしやったら。
藤田 青柳含めて、それをやったひとはいままでいないですね。
名久井 もしそんなことあったら、「わんこそばのエプロンつけるなー!」みたいに言うの?
藤田 言わないけど、それはとても面白い状況だね。でもそういうことされたらどういう反応するかな、ぼくは。されたことないです。
名久井 お客さんに女優さんいたら、藤田さんにやるといいよ。
藤田 なんで困らせるんですか(笑)
穂村 「幸福行きを二枚ください」っていう曲の歌が流れたと思うけれど。あの曲、僕が子どもの頃、北海道に「幸福駅」という駅があって、そこまでの切符を持つのがすごく流行ったんだよね。お客さん、みんな若そうだから知らないかもしれないけど。
名久井 でも頷いてるひとも結構いますね。
穂村 その駅の名前が出てくる芹洋子さんの歌があって、その歌をね、切符の説明をするために僕が口ずさんだんだよね。それがやっぱり使われてしまっていた(笑)初日はたしか青柳さんとデュエットみたいになっていたんだけど、二日目くらいから、青柳さんが先に歌い出す輪唱になっていた。それもすごく良くなっていたんだよね。あれはさすがに、指示してるんでしょ?
藤田 あれは、青柳と話し合いながらタイミング決めました。タイミングがすごく難しくて。
穂村 最初のデュエットではいけないってことにどうして気づけるの?
藤田 あの音源は穂村さんを取材したときに偶然回していた映像から音だけ抜き出したんですけど、穂村さんはあの歌を歌ってるだけじゃなくて歌を口ずさみながら、曲の説明をしてくれていたんですね。その音源を切り貼りして、穂村さんが歌ってるように編集したんです。だから本当はもっと歌のスピードが早くて、それを調整してものすごくゆっくりにしました。その音源に青柳が台詞を合わせていく稽古をしたんです。そうしているうちに輪唱が一番しっくりきたんじゃないかな。
穂村 すごいね。そもそも、この歌は本編の前後とはなんら無関係で、取材のエピソードの中に偶然出てきた話なんだよね。確か、父が昔お土産でどんなものを買ってきたかっていう話をした時に、箱根の寄木細工を買ってきたっていう話をしてたんだよね。その、寄木細工の中に何を入れてたのかという質問をされたから、「幸福駅行きの切符」を入れてたって話しをしたんです。
藤田 この話、すごくない? 寄木細工の中にそんなの入れる?
名久井 すごーい。そんなに大事だったんだ。
藤田 そのことにびっくりしたんだけど、僕。
名久井 寄木細工って、出すのすごい大変なやつでしょ?
藤田 そうそう。マトリックスとかキューブみたいになるやつ。
穂村 作品の中に寄木細工も出てこなくて、幸福行きの切符が何十万枚か売れたっていうエピソードまで話したのに、その話も出てこなくて、なぜか僕の歌が使われていたっていう。
藤田 穂村さんの『水中翼船炎上中』を読んでいると「サランラップ」という言葉がいくつもでてくるんです。僕の言葉でいうと、あれはリフレインだと思うんです。『冷蔵庫の麦茶を出してからからと砂糖溶かしていた夏の朝』という麦茶にまつわるお母さんとのエピソードも、何度かリフレインしているように読める。お母さんがご存命のころのチャプターと、亡くなったあとのチャプターにそれぞれ配置されているから、全然響きが違って読めるんです。なんでこんなことを穂村さんはできるんだろうって、手を震わせながら歌集を読みました。『サランラップにくるまれたちちははがきらきらきらきらセックスをする』という短歌についても考えましたね。劇中には「お父さん」も「お母さん」も「穂村さん」も「名久井さん」も登場するけれど、青柳はそれをひとりで演じているだけで、そして結局最後までひとりだとおもっていたのだけど、はじめて"ふたり"ということを意識し始めたのかもしれない。なので今年取り組むにあたって、新しい要素としてミッキーとミニーのぬいぐるみを小道具として使用したいと思ったり。さっきの寄木細工と幸福駅行きの切符の話って、お父さんがいて、穂村さんがいないと生まれないエピソードだから、ひとりじゃありえないなって。芹洋子さんの歌詞も、別々に育った二人で幸せになりましょうみたいな歌なので、あそこでその歌を青柳と穂村さんに歌ってほしいなと思いました。
名久井 なるほど。みんなひとりずつ出てきているんだけど、お父さんとお母さんだったり、わたしと穂村さんだったり、夫婦という関係性だけではなくいろいろ巡り合ってきている。確かに、今年のバージョンではそのことが分かりやすくなったっていう印象がありました。
穂村 今藤田さんが言ったように、作品の中での時間やその言葉のやりとりは、藤田さんは僕なんかよりはるかに高度に今日の演目でもやっていますよね。おしっこが飛ぶっていうのが冒頭で、リフレインされているフレーズがあるけれど、それはそのあとに出てくる「エイが飛ぶ」と繋がるんだよね。
藤田 劇中で使っている『海光よ 何かの継ぎ目に来るたびに規則正しく跳ねる僕らは』という短歌の「跳ねる」っていう言葉への関連性は意識してます。
穂村 僕の言葉だけではなくって、藤田さんが書いた部分や別の要素にある言語が、最後まで地面の下を流れていて、ラストシーンで一部ずつ顔を出していると思う。言語力だけでいってもすごい緻密さで高度なことをやっているなって。
藤田 ありがとうございます。でも、それって戯曲的な考え方でもあるのかもなと最近は思っています。戯曲は1時間半とかの詩でもあるので、もちろんそれぞれワンシーンとして成立させることも大切なことかもしれないですが、リフレインっていう分かりやすい繰り返しじゃなくても、前に聞いたことあるフレーズがポンと置かれるだけで、お客さんは上演時間の冒頭に戻れたりするのではないかと思っているんです。
穂村 もう一つ聞いてみてもいい? 核心に触れるわけではないけど、なんで着ぐるみのティモシーを出そうと思ったの?
藤田 この舞台上はこんなにものに溢れているけど、青柳の私物ってダンボのぬいぐるみぐらいなんですよね。あとは僕の私物だったり、関係者のものです。『ダンボ』の映画の中で、ティモシーはダンボが外に出るための手伝いをしてあげるんですよね。そのストーリーが僕のなかで印象深くて。今回の作品では、ティモシーが空っぽになった部屋に残って、ダンボだけを外に出してあげるみたいなストーリーをやりたかったんだと思います。あんまりネズミがティモシーに見えてないからうまくいってないかもしれないけど……。自分のなかではそういうのがありますね。

穂村 じゃあ、ティモシーが写真を撮るのは?
藤田 写真って、記録というか、ここに誰かが居たっていうことが分かりやすく反映されるものじゃないですか。写ったものに特別なものが写っていなかったとしても、ここの、この時間だけを切り取るみたいなことができる。おそらく、作品に出てくる女の子は部屋にひとりでいただろうし、多分誰にも写真を撮られていなかっただろうけど、その女の子の時間が写真というフレームの中に残るみたいなことがあってもいいのかなと。言葉じゃないところで、やりながら思ってましたね。
名久井 私は引っ越す時に写真を撮るので個人的には、すごく引越しを感じました。
穂村 空っぽの部屋の写真を?
名久井 さっきまでの部屋と空になった部屋って、全然違うじゃない?
藤田 確かに。
穂村 思い出的な?
名久井 うん。単純に面白いっていうか、興味があるっていうか。
穂村 そしたら、今回ティモシーが、女の子のことを撮影しているのは、そんなに疑問には思わない?
名久井 うん。そうだね。